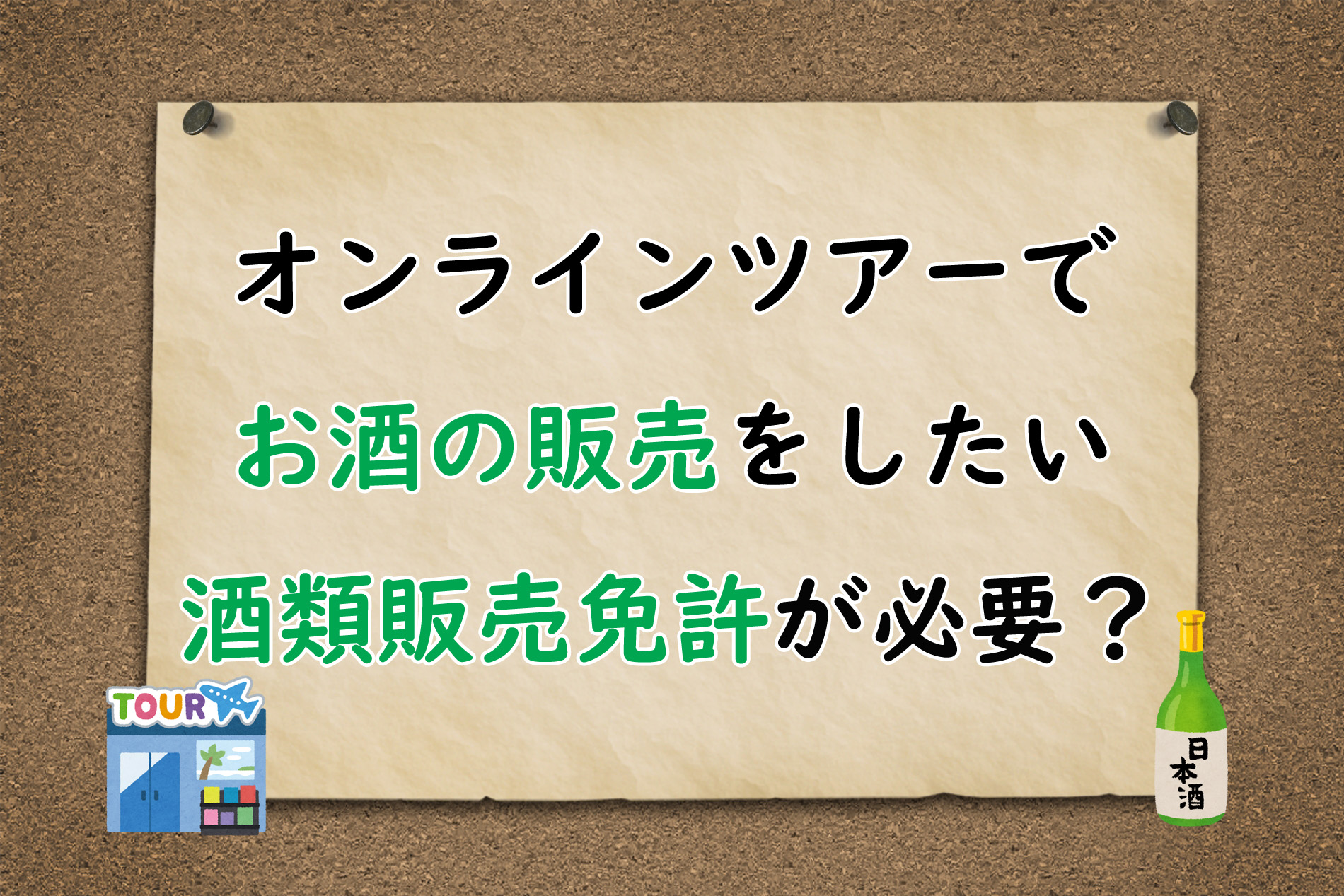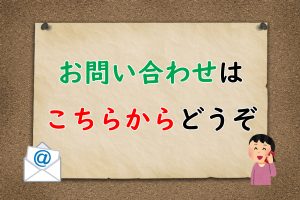コロナ禍で人の移動は制限され、旅行業界は大きな影響を受けています。
その中で、新しい試みとしてオンラインツアー商品の造成に取り組んでおられる旅行会社も多いのではないでしょうか。
オンラインツアーの内容は様々ですが、特に日本各地の名産品をツアー参加者に事前に送付。
ツアー当日はそうした名産品の生産者の話を聞きながら、同一の時間や体験を共有する、といったものが特に人気です。
そして、名産品として地酒や地ワインを提供して、それをツアーの目玉にしたいというニーズも強くあります。
オンラインツアーそのものについては、宿泊や運送手段の手配が絡まない場合は、旅行業としての登録は不要です。
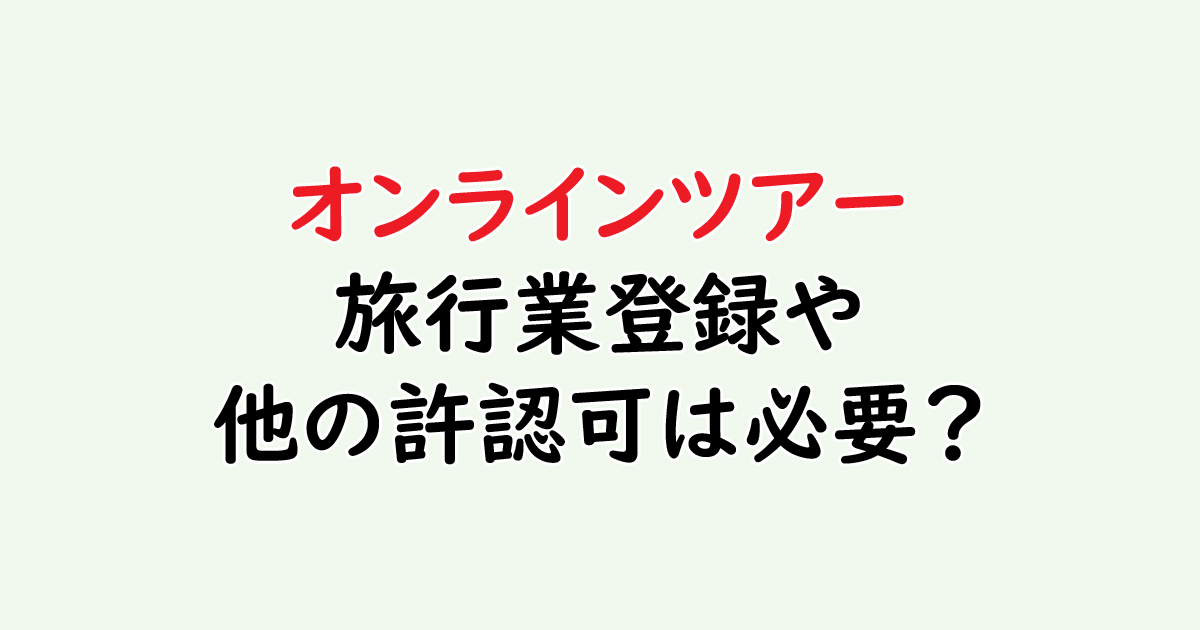
しかし、こうした物販、特にお酒の販売を伴う場合にはビジネスモデルの検討が必要です。
というのも、ビジネスモデル次第では酒類販売免許の取得が必要になるからです。
本記事では、オンラインツアーでお酒の販売をする際に気を付ける点について解説していきます。
オンラインツアーでお酒を販売する場合の注意点
酒類販売免許の種類と取得方法
酒類販売免許が不要なビジネスモデル
なぜ酒類販売免許の取得が必要なのか
お酒には税金がかかります。
これらの税金を確実に徴収するため、お酒の製造と販売業には免許制度が採用されています。
そして、酒類の販売方法などによって免許の種類は分かれています。
オンラインツアーで酒類を販売するケースとして、
①酒類在庫をツアー主催者が買い取って、主催者から参加者に発送するパターン
②蔵元やワイナリーから参加者に発送するパターン
といったビジネスモデルが考えられます。
どちらのパターンであっても、酒類販売免許が必要になってくる可能性はあります。
細かい設計によって論点が変わってくるので、詳細はぜひ1度、専門家や税務署に相談してみてください。
当事務所でも、ご相談を承っております。
旅行会社が酒類販売免許を取得できるのか
オンラインツアーを主催するのは、旅行会社であることがほとんどだと思います。
旅行会社は資産要件や人的要件をクリアして登録を受けることができます。
では、そうした旅行会社が酒類販売免許を取得することは可能なのでしょうか?
結論から言えば、旅行会社でも酒類販売免許を取得することは可能です。
もちろん、免許取得のための条件があるので、そうした条件をクリアしていく必要があります。
酒類販売免許の概要
免許の種類
酒類販売の免許は、大きく分類すると
①小売の免許と②卸売の免許に分けられます。
ここでいう「小売」とは、一般消費者や飲食店に販売することをいいます。
一般的には飲食店などの事業者に販売することを「卸し」と言いますが、酒類販売の世界では種類を一般消費者に提供する飲食店向けに販売することも「小売」というので、少し注意が必要です。
一方で、「卸売」とは仕入れた酒類を小売業免許を持った事業者や、酒類製造免許を持った事業者に対して販売することいいます。
小売業免許は、さらに一般小売と通信販売小売に分類することができます。
卸売業免許は、全酒類卸売、輸出入卸売、洋酒卸売、ビール卸売といったものに分類することができます。
それぞれの免許で、販売方法や販売できるお酒の種類、最低販売量などが決められています。
別の記事で、酒類販売免許の全体像について解説しているので、そちらもご参照ください。
https://yachida-office.info/alcohol-selling/shuhanmenkyo/
オンラインツアーで必要な免許
さて、それではオンラインツアーではどんな免許が必要になるのでしょうか。
もちろん、各ツアーの実施方法で多少は異なると思いますが、一般的には通信販売酒類小売業免許の取得が必要になる可能性が高いでしょう。
インターネット経由で、2以上の都道府県の消費者等を対象とする場合は、通信販売用の免許が必要となります。
あるいは、ビジネスモデルによっては酒類販売媒介業免許という、酒類販売免許の中でも少し特殊な免許が必要になる可能性も出てきます。
免許の取得方法
酒類販売業免許の取得方法の詳細については、個別の記事を確認していただきたいと思います。
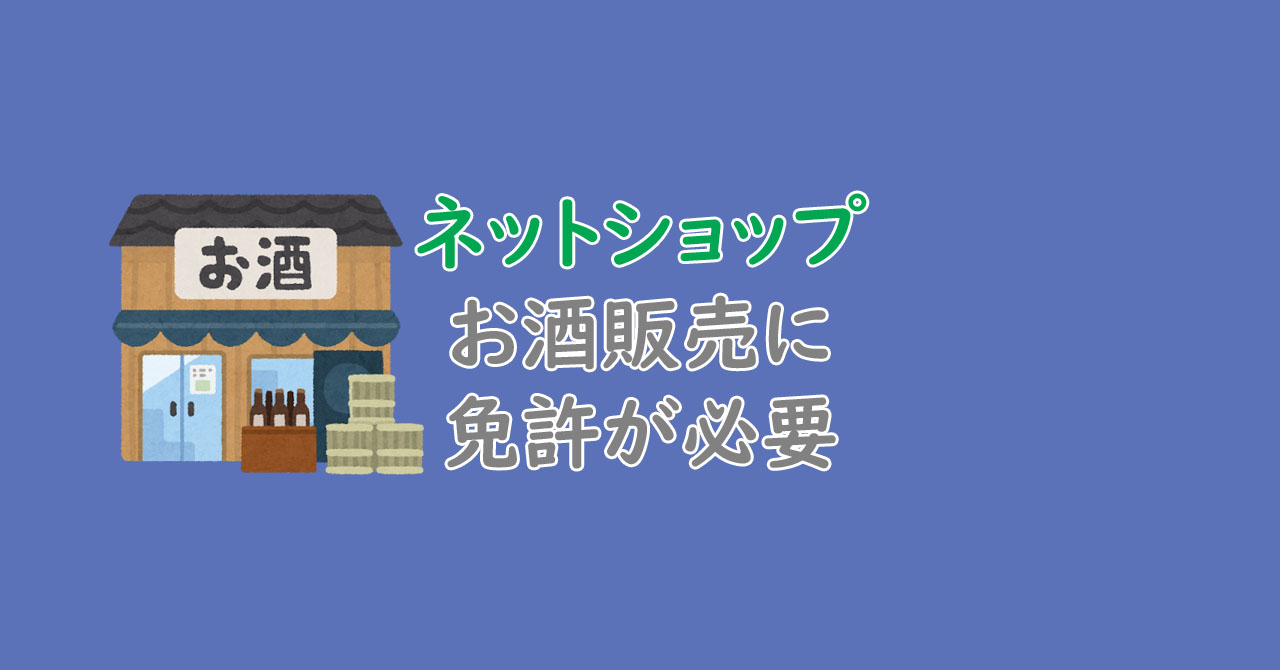
仮に通信販売酒類小売業免許を取得するためには、
①人に関する条件
②販売場に関する条件
③経営基礎条件
④需給調整条件
の4つの観点から免許を受けることが適当である、と証明していく必要があります。
①については、申請関係者の中に法令違反や税金の滞納、酒類免許の取消を受けた人がいると、免許を取得することができません。
③の経営基礎は、資産に関する条件や、酒類販売管理者の配置などが求められます。
④は、通信販売免許の場合は、年間出荷量が3000キロリットルを超えるお酒については通信販売できない、ということになっています。
こうした条件を全てクリアしていること確認したうえで、管轄税務署に対して申請をしていきます。
まとめ
申請すれば誰でも免許を取得できるものではなく、事業計画の内容や資金計画などによって免許の取得可能性が変わってきます。
また、申請してから免許を取得するまで、2ヶ月ほどの審査期間があります。
申請した内容に不備などがあれば補正が発生し、その補正が終わるまでは審査が止まった状態になるため、免許が下りるまでの期間はどんどん後ろに伸びていきます。
あなたが考えているビジネスモデルに酒類販売免許が必要か、そしてスムーズに免許を取得してすぐにお酒を販売するオンラインツアーを開始したい、という場合は、ぜひ一度専門家にご相談くださいませ。
問い合わせフォームよりご相談いただけます。
当事務所は観光法務の専門事務所として、ツアー実施に必要な酒販の免許申請サポートにも対応しております。
あなたからのご連絡をお待ちしております。